フィールドワークなどの現地調査を海外で行なってきた研究者にとって、新型コロナウイルスをめぐる昨今の状況は研究の進捗を滞らせる厄介なものです。しかし、文化人類学者の小田博志さん(文学研究院 人文学部門文化多様性論分野 文化人類学研究室 教授)にその状況について尋ねると意外な答えが返ってきました。

「飛行機で離れた土地に行くのが人類学者のフィールドワークだとしたら“商売あがったり”の時代になったと言えます。しかし、人類学者のやることは「あたりまえ」を問い直していくということ。だから、あらゆるところ、今生きているここでもフィールドワークできる。これまで人類学は人間だけを見ていたのが、近くにいる人間以外の存在ともコミュニケーションできるということがより実感されてきた。こうしてコロナの状況は視野が広がる「チャンス」だとも言えるんです。」

「チャンス」という言葉が新型コロナウイルスをめぐる状況を形容することに使われるのに違和感をもつ方もいるでしょう。しかし、少なからぬ人々が同じ「チャンス」という言葉を用いてこの状況を表していることがたびたび見受けられます。そして、小田さんも、この「チャンス」という表現をもちいて、コロナ禍の状況について語ってきました1)。では、この状況は、小田さんにとって、なぜ「チャンス」と言いうるものなのでしょうか。日常の「あたりまえ」を問い直す文化人類学の視点から、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況をとらえ直してみましょう。
【原 健一・CoSTEP博士研究員】
小田さんは新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を「好機(チャンス)」と表現しています。これは一見したところ奇妙な表現にも思えるのですが、どのような意味で「チャンス」という言葉を用いているのでしょうか?
新型コロナウイルスをめぐるこの状況は「グローバル資本主義をこれ以上進めていてはいけない、スローダウンしなさい」といういわば「地球の声」だと感じます。これまで多くの科学者も警告を発してきたように、このままグローバル資本主義を押し進めていくことは、将来世代が生きてはいけないような破局的な状況へと向かうことです。森林を伐採したり、地下資源を採掘したりするほどGDPの値がプラスになる。大量にモノを生産してそれを売りさばき、廃棄物が出るほど、温暖化が進むほど、海がマイクロプラスチックで覆われるほど、経済が成長する……このあり方を変えないといけない。

こうした近代以降の文明のありようは人間が作り出したものです。したがって、人間自身がストップするしかない。けれど結局止められなかった。それをコロナウイルスという目に見えない存在がつかの間ではあれピタリと止めてくれました。ウイルスが人類に働きかけ、私たちの経済活動を止めたのです。今のところ、「経済活動ができるもとの状態にまた戻ろう」という動きが強いように見えます。生活のためにそれが必要な方はもちろんいらっしゃいます。けれども、これまでのような経済活動を続ければ、グローバル気候変動が悪化するのは目に見えています。今は方向転換をするためのモラトリアム(猶予)期間だと思うのです。「いのちか経済か」という今の二者択一を止揚して、いわば「いのち育む経済」に移っていく必要があるように思います。
「いのち」を育む経済…? それはどのようなものなのでしょう。
ヴァイツゼッカーというドイツの医学者が「生命それ自身は決して死なない、死ぬのはただ、個々の生きものだけである」と言っています 2)。無限定のいのちが自らを限定して、私やあなたのような人間、あるいはこの木やあの鳥といった個々の生きものとして表現しています。そうした個々の生きものの寿命には限界があるけれど、無限定のいのちそのものは決して死ぬことはない。ヴァイツゼッカーはそういう生命論を展開しました。
こうした考えは、ギリシアの古代哲学や仏教といった他のさまざまな文脈でも共通して見られます。しかし、近代は無限定のいのちに切れ目を入れて「自然/文化」に分割しました。この分割を前提に近代文明は成り立っています。そこでは、自然の状態から離れていくことが「進歩」「発展」とみなされます。そして、人間は自らを自然を支配する主体だと錯覚してきました。
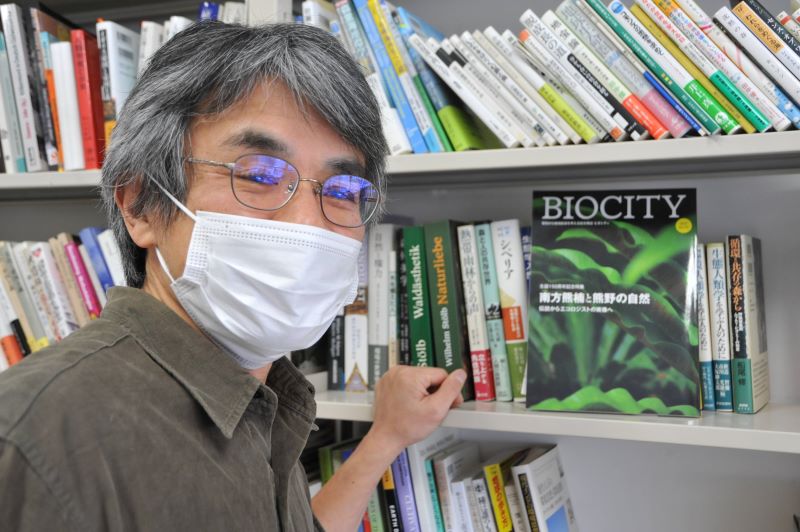
森羅万象、あらゆる生きものは互いにつながり合っています。この「いのちの網の目」自身が生きていて、そのつながりの一部として人間も生きている。それにも関わらず、そこから自分たちを切り離して、自然を客体として都合のいいように利用してきたのが近代という時代です。そのしっぺ返しが、気候変動や新型コロナウイルス感染症として現れている。もういちど、私たちもこの大きないのちのつながりの中にいるんだということを思い起こして、そこに立ち還るときが来ています。このつながりを断ち切る経済ではなく、「いのちの網の目を育む経済」こそがこれからの時代の基礎となるべきものです3)。
そのような、個々の生きものの根底にある「いのちの網の目」が見過ごされてしまっているのが近現代という時代なのですね。
最近、さまざまな分野の人々が、このような考え方に言及し始めています。カナダのブリティッシュコロンビア大学のスザンヌ・シマードという森林生態学者がいます。森の木々というのは、地上だけを見ると木がいっぱい立っていて、互いに日光を奪い合って競争しているように見える。だけど、実は地下では菌糸によって木々の根っこは互いにつながって、栄養とか防御のための情報などのやりとりしている、つまり木々はコミュニケーションを取っていることが明らかになっています。つまり、一本一本の木ではなく、森が一つの生きものとして生きている、共生のネットワークなのです。そこで生きているのは、木々だけではなくて、微生物、昆虫、動物、魚などの多種多様な生きものたちです。ここにも「いのちの網の目」の中で個々の生きものが生きているということが表れています4)。
ここでいう「いのちの網の目」は人間も含んでいます。だから文系(人文社会科学)と理系(自然科学)の両方に関係している。それを人間の領域と、自然の領域に人為的に分けることで、文系と理系の区別は成り立っています。しかし人間ぬきの自然を考える自然科学と、自然ぬきの人間を考える人文社会科学というのはどだい「不自然」です。つまり大学においても、文系と理系という枠組みを超えて「いのち」をそしてそのつながりをトータルに捉える必要があると思うんです。
そのような世界観から見たときにウイルスはどのような存在者になるのでしょうか。
ウイルスは外側からやってくる敵で、それを攻撃するという思考パターンも、人間と自然の分割を前提としています。でもウイルスも、その宿主のコウモリ5)も、コウモリの住処である森も、そして人間も網の目の中で関わり合っていて、外側はありません。ですからその部分(新型コロナウイルス)だけを捉えて、それをやっつけようとしても、次は別の形で違った問題が出てくるでしょう。問題が根本的に解決していないからです。人間が自然を思うようにコントロールするという根本的な問題の一症状として、新型コロナウイルス感染症は起こっているように思えます。
「いのちの網の目」すなわち生きとし生けるもののネットワークの中で、人間もその一部として生きているというイメージは、実は目新しいものではなく、古くからあるものの見方でもある。それは先住民族が生きてきた、あらゆるものにスピリットがあり、世界全体が生きているという捉え方でもあります。このような古くて新しいものの見方に「いのち」の本来の姿が表されていると思うのです。それを自然科学が最近再発見しています。この「いのちの網の目」の中で人間も生きているという、古くて新しいものの見方を回復させる「チャンス」が今訪れているのです。

注・参考文献
- 北大文化人類学研究室のサイトにある以下のメッセージが参考になります。小田博志 2020:「緊急メッセージ ー 新型コロナウイルス感染症と文化人類学」『北海道大学大学院文学院文化多様性論講座文化人類学研究室サイト』(2021年4月5日閲覧).
- V・v・ヴァイツゼッカー(木村敏・浜中淑彦訳邦訳)1975: 『ゲシュタルトクライス――知覚と運動の人間学』みすず書房, 3頁.
- このような「いのち」のとらえ方については以下も参考になります。小田博志 2020:「コロナ後の「生類の平和」のために」『小田博志研究室ウェブエッセイ』(2021年4月5日閲覧).
- シマードはこのような考え方を以下のTED講演の中で語っています。Simard, Suzanne 2016: “How trees talk to each other” TED, 2016.8.31(2021年4月5日閲覧).
- コウモリである可能性が高いといわれていますが、まだ確定してはいません。詳しくは以下を参照してください。WHO 2021: “Origins of the SARS-CoV-2”(2021年4月9日閲覧).
