
起こりえるかもしれない危機、あり得るかもしれないリスク、未来を今から想像するのは簡単ではありません。ただ、事が起こってから後悔はしたくない、北大では未来を見据えて走り始める「いつかのための研究」があります。この「いつかのための研究」シリーズでは、CoSTEPが北大の複数の研究組織とコラボレーションし、来るかもしれない「未来」のために、「今」から始める研究について迫ります。
シリーズ1回目は、北大に新たに生まれたワクチン研究開発拠点(Institute for Vaccine Research and Development: 以下IVReD)の拠点長・教授である澤洋文さんに、未来のパンデミックを見据えて始まった北大でのワクチン開発や感染症対策についての研究について伺いました。
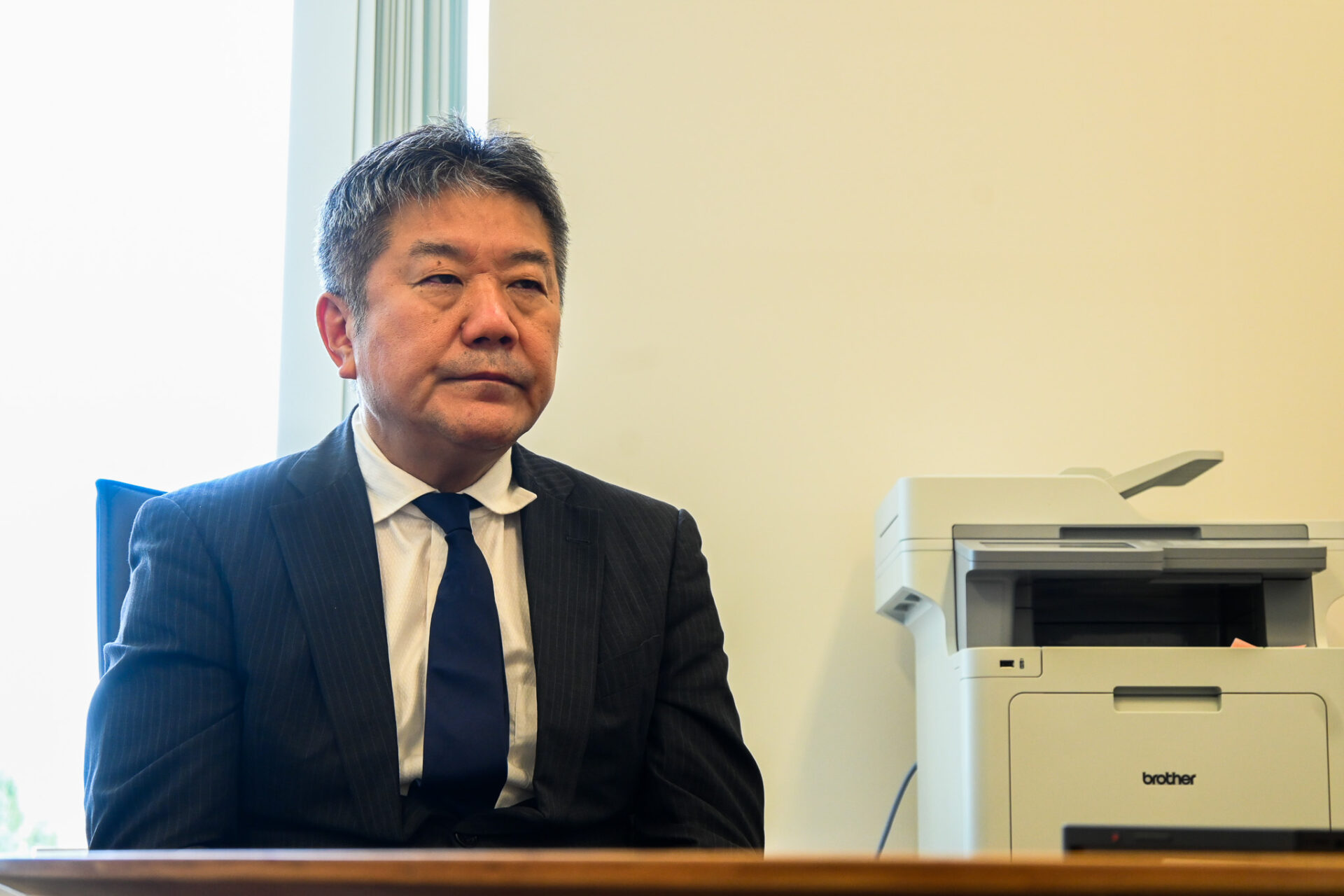 IVReDの拠点長の澤洋文さん
IVReDの拠点長の澤洋文さん
――新型コロナウイルス感染症のパンデミックは私たちの生活に深い爪痕を残しました。その反省も踏まえてということなのかもしれませんが、そもそも北大にワクチン研究開発拠点ができた背景について教えてください。
澤 IVReDは日本の複数の大学にできたワクチン開発拠点の一つです。日本医療研究開発機構(AMED)の下、未来のパンデミックに備えて、フラッグシップ拠点である東京大学を筆頭に、シナジー拠点として長崎大学、大阪大学、千葉大学、そして私たちの北海道大学に設置されました。感染症研究においてはそれぞれの大学で違った強みがありますので、それらの強みを持ち寄って、感染症研究、そしてその研究の社会実装まで見据えたワクチン開発や治療法の確立までを目指しています。
――北大の強みとはなんでしょう?
澤 シンプルに言いますと、人獣共通感染症への取り組みです。北大には人獣共通感染症国際共同研究所があり、私もそこで研究を進めてきました。感染症には人獣共通のもの、つまり動物から感染するものがかなり多いです。人獣共通感染症を理解するためには、医学だけでなく、獣医学や生理学など幅広い観点からの検討が必要で、その研究を長年やってきたということは北大の強みです。
また新たな人獣共通感染症が発生しやすいアフリカでの研究実績も豊富です。人獣共通感染症の発生は、ヒトと動物の接触が多い熱帯地方に多い傾向が有ります。北大ではアフリカのザンビアに研究拠点を持ち、ザンビア大学と長い間共同で研究をしてきました。
 ザンビア拠点では研究者育成と感染症研究が行われている
ザンビア拠点では研究者育成と感染症研究が行われている
――今回、さらにその研究を加速するということなのですね。
澤 北大全体で、研究を進めていくという点がとても大事です。人獣共通感染症の研究はこれまでヒト側の研究において課題がありました。しかしIVReDが設置された結果、北大病院や医学部との連携も進むようになり、ヒトと動物の研究の連携がつながったと言っていいでしょう。
ワクチンを開発する際には、病原体と宿主の関係、感染の経路、ヒトの体内で起こる感染のメカニズムなど複数のフェーズの検討が必要です。また社会実装化に向けては臨床実験も必要不可欠になります。今回の拠点が設置されたおかげで、動物や病原体側の研究と医療側の研究との連携体制ができたと思います。
――現在、IVReDが研究対象にしている感染症はなんですか。
澤 IVReDはコロナウイルス感染症や結核、そしてインフルエンザの研究が進んでいます。
ワクチン開発には病原体の研究、そしてその病原体が宿主の体内に入り、宿主の体内が何らかの反応する病気の研究といった基礎的な研究も必要不可欠です。そしてその反応も宿主によって異なります。宿主の中でどのような反応をもたらすのかを分析したうえで予防法を考えていく必要があるのです。加えて北大では、多様なインフルエンザウイルスを系統保存した、インフルエンザウイルスのライブラリーを持っており、そのような包括的な研究が行われているところも強みの一つです。
また感染症は病気の研究だけでは十分ではありません。社会学や環境学などの感染を予防したり、公衆衛生の仕組みを確立したりと、多分野の研究との協働が必要になります。最近、感染症の対策は、人間だけでなく、人間以外の生き物や環境全体の健康を考え取り組む「ワンヘルス・ワンワールド」という概念が提唱されています。そのような総合的な対策は、北大がいわゆる総合大学だからこそ可能になります。
 ビックデータやAIなど新たな技術の活用もこれからの課題と澤さんは語ります
ビックデータやAIなど新たな技術の活用もこれからの課題と澤さんは語ります
――最後に、澤さんがこのIVReDがこれから目指す活動はなんですか。
澤 今、IVReDには若い研究者の方々が集まってきています。若い研究者の方々が、この時代に活躍できるような場を作るということが一つの目標です。学術的価値だけでなく、社会に貢献できる良い成果を導き出す研究をしていきたい、というのが今のスローガンです。
大学で進めている研究は基礎研究が中心です。ただ社会とのつながりが見えにくい基礎研究はどうしても大学の中に留まる事が多いです。IVReDを通じて、若い方々が新しい研究にチャレンジできる場、そしてその挑戦からこれからの社会の健康に貢献できるような道筋を作っていきたいと考えています。その環境づくりこそ、IVReDのこれからの目標です。
