竹内繁樹さん(北大客員教授1))、岡本亮さん(北大電子科学研究所助教)、小野貴史さん(同博士研究員)の研究グループは、互いに相関した光子のペアを光源として用いて、「標準量子限界」という物理学上の限界を超えた感度をもつ光学顕微鏡を世界で初めて実現しました(本研究は “Nature Communications” 誌に2013年9月12日に論文として掲載されました)。いったい、どのような研究なのでしょうか。竹内さんたちに話を聞きました。
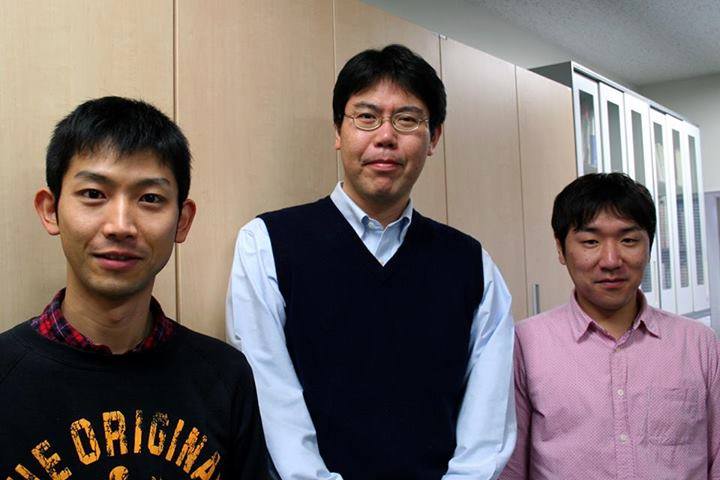
なぜ高感度の顕微鏡が必要なのでしょうか
光学顕微鏡は観察対象に光をあててミクロの世界を捉えます。しかし、倍率を高くすると使える光が少なくなってしまうという問題があります。また、強い光をあてると傷んでしまう標本もあります。そのため、いかに少ない光で観察できるか、言い換えると、高い感度をもつ顕微鏡をつくることが求められているのです。
今回私たちは、光子の「もつれ」を用いた「量子もつれ顕微鏡」を世界で初めて実現しました。従来の光学顕微鏡に用いられている通常の光には、ある物理学的な限界があります。光が少なくなるとノイズが多くなり、像を捉えるのに必要な光の信号が識別できなくなるのです。この光の信号とノイズの大きさが等しくなる光の強さが「標準量子限界」です。しかし、「量子もつれ光」を用いれば、この標準量子限界よりも弱い光でも観察が可能になる、と私たちは考えました。
(量子もつれ顕微鏡の心臓部。右側の青い機器が量子もつれ光子を発生させる光源)
光は光子と呼ばれる粒子からなっていますが、この光子の性質を理解し、操ることで、高感度の量子もつれ顕微鏡が可能になります。量子力学をはじめとする現代物理学の発展と、ナノテクノロジーの進展によって、いまや光子を1個1個発生させたり閉じ込めたり、さまざまな仕方で操作したりできるようになってきています。

当てる光に違いがあるのですね。ではどれくらい高感度になったのでしょうか?
量子もつれ光によって、レーザー光による従来型顕微鏡の1.35倍の感度を達成し、「標準量子限界」を突破したことを検証できました。今回の実験方法の場合、理論上の上限は1.41倍の感度です。それに近い値を出すことができました。
この検証にはガラス基板の上に作った「Q」のレリーフを観察対象に用いました。「Q」の縦横の大きさは0.5ミリメートルですが、厚さはわずか100万分の17ミリメートル、原子にして100個程度しかないという、極めて薄いものです。この「Q」を量子もつれ顕微鏡で観察したところ、通常のレーザー光を用いた観測と比較して、より明瞭にQの文字を観察することができました。

私たちの研究室では良質な『量子もつれ光子』をペアで発出させる世界最高レベルの技術を培ってきました。その利用が今回の成功のカギになったのです。
ところで…ペアの光子の「量子もつれ」とは?
二つの光子aとbが空間的に離れていても互いに関連した性質を示し、一方の光子aの状態Aを観測することで、もう一方の光子bの状態Bが決定されることです。逆に言えば、観測するまでは光子aとbはそれぞれAとB両方の状態にあると言えます。この量子力学的現象を用いることで、少ない光子でも高い感度でサンプルに関する信号を得ることができるのです。

さらに感度はあがるのでしょうか。今後の展開は。
今回の実験では一つのペアの光子もつれを利用しましたが、今後は、より多くのペアで行い、標準量子限界を大きく超える感度を実現させていく計画です。

量子もつれ顕微鏡の開発によって、これまで感度が不足していたため観察できなかった、生体細胞内部の変化や、たんぱく質の結晶化過程の解明などに応用できるのではないかと期待しています。また、弱い光量でもより明瞭に対象を観測できるため、光量すなわちエネルギーが少なくて済み、将来的には低コスト化にもつながると考えています。
実は私たちの研究室では、量子情報科学を中心に、光量子コンピュータによる量子暗号通信などを研究しています。今回の研究は、量子技術の一つを顕微鏡に応用したものなのです。このように、光子(フォトン)を操ることで、様々なことが可能になります。私たちは光子を自在に操る、光子のお手玉師 “フォトン・ジャグラー”を目指しているのです。
注
- 竹内繁樹さんは現在、北海道大学客員教授であり、京都大学工学研究科教授。2014年2月まで北海道大学電子科学研究所教授。
