2022年10月27日に好評のうちに終了した苫小牧研究林の体験ツアー。どのような背景がこの企画にはあったのでしょうか。ツアー終了直後に岸田治さん(北方生物圏フィールド科学センター 准教授)、中村誠宏さん(同 教授/苫小牧研究林長)、植竹淳さん(同 准教授)にインタビューしました。
3人のお話からは、今まさに苫小牧研究林が大きく変わろうとしていることが伝わってきました。苫小牧研究林が抱える課題とは何か、新たな研究林のあり方とは?
【小辻龍郎・CoSTEP本科生/環境科学院修士1年】
とても刺激的なツアーでした。手応えはいかがでしたか。
岸田: 今回は一般の方に参加していただいた初めての有料ツアーでした。今まで学生実習などで積み重ねてきたプログラムを凝縮させたので、参加者からもそれなりに満足いただいたと感じています。

今回のツアーは岸田さんが企画の中心とのことですが、工夫した点は。
岸田: 大学の実習等を使いながら何回も予行演習をしたことですね。やはり参加費を頂いている以上、できる限り満足いただけるようなものにしなくちゃいけないっていう思いがありまして。そして「苫小牧研究林ならではのプログラムを」という思いが強くありました。なので、PITタグなど特殊な機器を使った魚類調査や、全国にも苫小牧研究林にしかない林冠クレーン試乗を盛り込んだプログラムにしようと試行錯誤しました。

中村さんは、今後も市民向けのプログラムを開催したいと考えていますか。
中村: 研究に支障のない範囲でやっていけたらと思います。今回のツアーのような「自然と触れ合いながら自然を知る」教育プログラムは、環境問題などを考えるきっかけとして重要ではないかと考えています。特に幼稚園から高校生までの子どもたちは、SDGsやサステナブルという言葉は知っていると思いますが、それを自分事として考える機会が少ないのかなと。そういったきっかけをプログラムとして提供できることが、我々の強みかなと考えています。
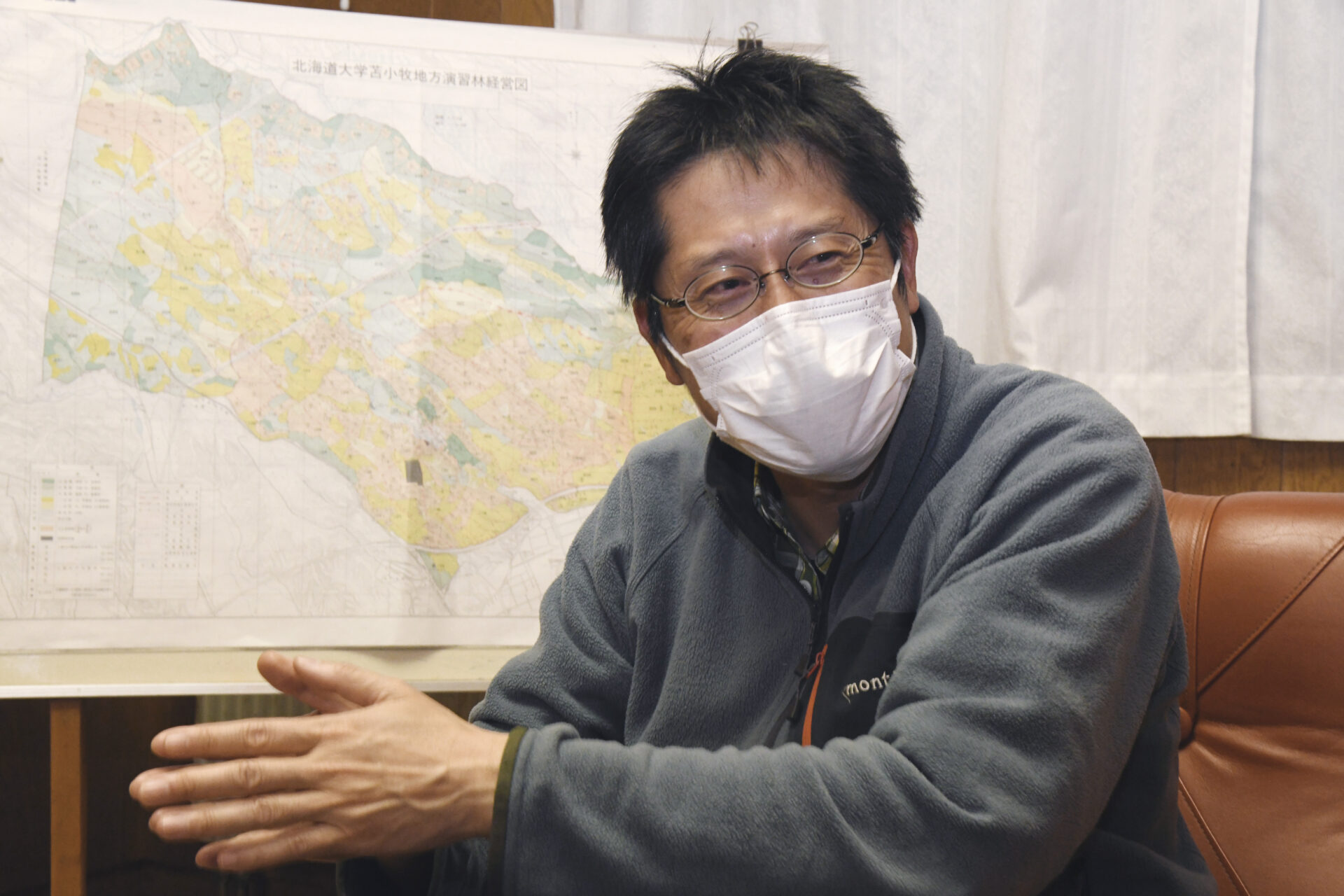
こういった企画を継続するためには研究とのバランスも必要ですね。
岸田: 難しいですね。基本的には研究第一ですが、一方で研究しやすくするためにもこういう活動が必要だとも考えています。企業さんから研究経費をご支援頂けることにつながるかもしれませんので。
中村: 私自身は苫小牧研究林の林長以外にも和歌山研究林の林長も兼務しています。恥ずかしながら、研究とそれ以外の仕事のバランスはあまりとれていないです(笑)。
研究林は研究の場ではありますが、一部は自由に出入りできることもあまり知られていないようです。植竹さんはその点についてどうお考えですか。
植竹: 私もその点をどうにかしたいと考えています。近所の方々には割と浸透していますが、多くの苫小牧市民は「大学研究林は入ってはいけない場所」というイメージがあります。だから「もっと気軽に入れる場所だよ」と発信する必要があります。最近は新聞社さんから取材も来ているので、立入禁止のイメージも改善されていくとは思います。

多くの市民に対する研究林の認知度向上が必要になるということですね。
植竹: そうですね。今回のようなイベントをきっかけに、実際に来ていただくことが何より大切なのかなと。どういう仕組みづくりをすればより情報を発信できるかを、この冬の間に熟成させて、来年の春や夏に新たな試みに繋げたいですね。

岸田: さらに、大学生や大学院生に教えるような内容のプログラムも、より多くの一般市民に向けてやりたいと思っています。なるべく生態系を壊さずに魚類調査をしたり、野生の動物や昆虫のモニタリング調査をしたり。研究者は物事の理解のためにこのような研究をやっていることを知ってもらいたい。そうすることで、各々の物の見方や、自然の見方が変わってくると思います。


研究林で培ったノウハウを多くの人たちに価値として提供していくということですね。いつ頃から今回の企画を考え始めていたのでしょうか。そのきっかけは?
岸田: 1〜2年前からですかね。モンベルの方々との企画打ち合わせは2021年の冬から進めてきました。きっかけとしては、高校生や一般市民に対して教育を提供していたときに、うちの技術系職員の力量があまりにすごくて、そこに引き込まれてくる高校生や一般市民の方々が多かったんです。それでこれは活かせるのではと感じました。
なるほど、技術系職員さんの力ですね。
岸田: 私は苫小牧研究林の技術系職員の技術力にすごく敬意を持っています。ひとつひとつの作業にすごく習熟しているんですよね。例えば魚のおなかにPITタグを入れる作業は初心者の方は中々難しいのですが、技術系職員は3秒くらいで素早く入れることができます。自信を持って作業することで、市民の方々に普段体験することのない世界を伝えることができるんじゃないかなと。




技術系職員の皆さんと課題を解決していくために重要な要素は?
中村: やはり研究林内部の一体感とチームワークが重要だと思います。一人のトップが色々考えるのではなく、研究林の皆さんの各々の知識や経験を持ち寄ってコミュニケーションをとりながら課題解決をしていくと良いのかなと。そうすることで、色々なアイデアが有機的に繋がって、今回のイベントみたいに新しいアイデアが実現しやすくなると思います。
岸田: 私も同じ考えです。ツアーをきっかけに、北大の研究林が市民に向けた教育の場として良いコンテンツを提供できるということを知っていただきたいですね。また別の形で、イベントを仕掛けていきたいと考えています。
植竹: 研究林側と市民側の相互作用も重要だと思います。今までは、大学は大学、市民は市民という感じでお互いに一切関係していませんでした。その垣根を少し取り払って「研究林はこういう場所!」というのを見せて、それに対する市民の方々からのアクションを上手く吸収することで相互作用が生まれることを目標にしています。
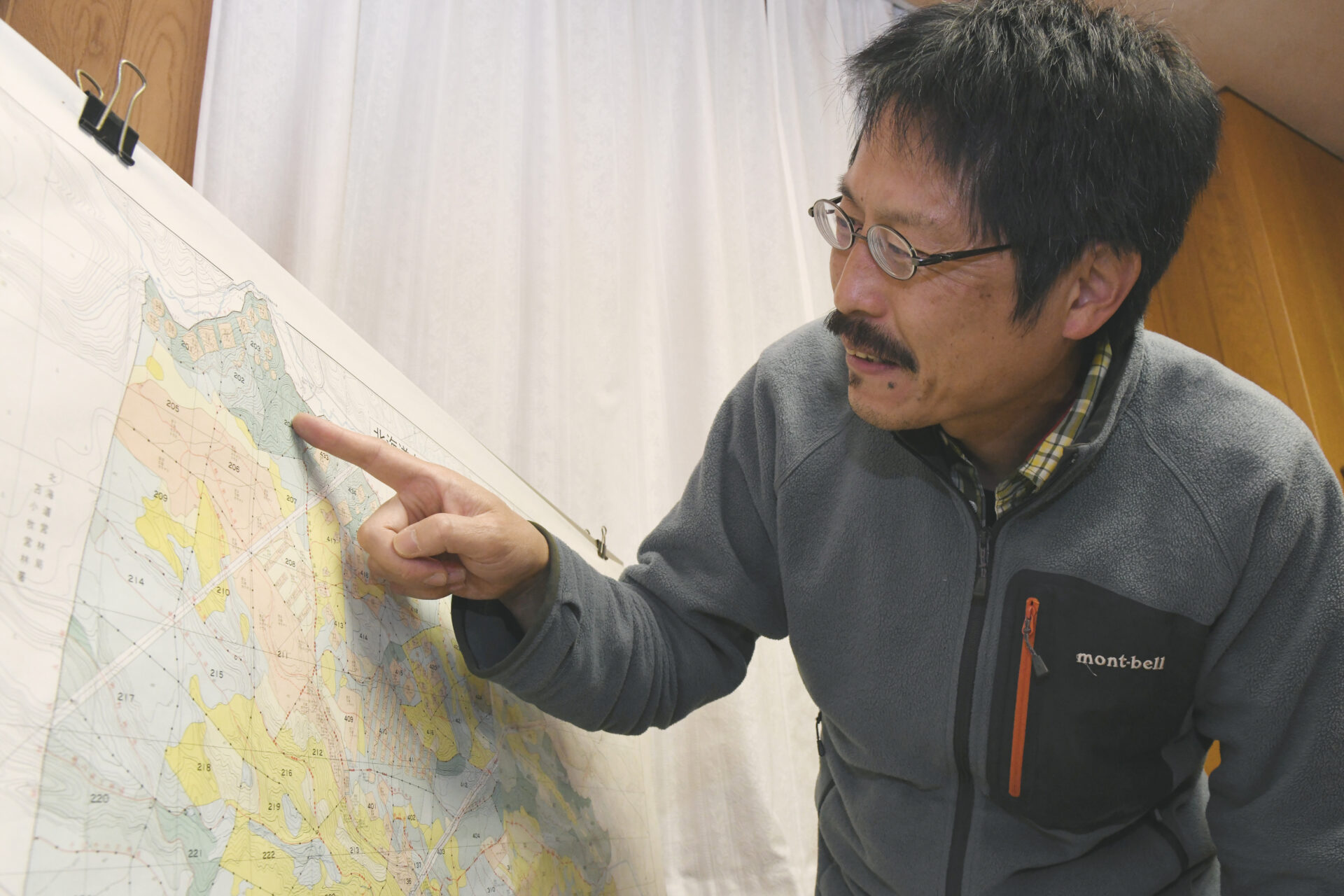
研究林スタッフのチームワークと市民との相互作用が重要なのですね。研究林の今後について考える良いきっかけになりました。ありがとうございました!
研究林の認知度向上、研究林の技術系職員と教員のチームワーク、既存の考え方にとらわれないアイデア、市民との相互作用。インタビューを進めていくに連れて、研究林の現場で働いているからこそ見えてくる課題点や、アイデア、可能性についてお話を伺うことができました。
今回のモンベルツアーは、単に研究林の新しい試みの一つではなく、市民と大学の新たな関係性を模索する実験的な取り組みだったと言えるでしょう。苫小牧研究林を起点に、大学での新たな学びの形が今後も次々生まれ、大樹のように育つことを願って、本記事を締めたいと思います。

注:
- 教員や学生の教育研究を直接支援する技術系の一般職は「教室系技術職員」とよばれ、技術専門員、技術専門職員、技術職員があります。また、技能又は労務的な業務を担う技能職として技能職員があります。記事の中ではそれらをまとめて「技術系職員」と記載しています。
