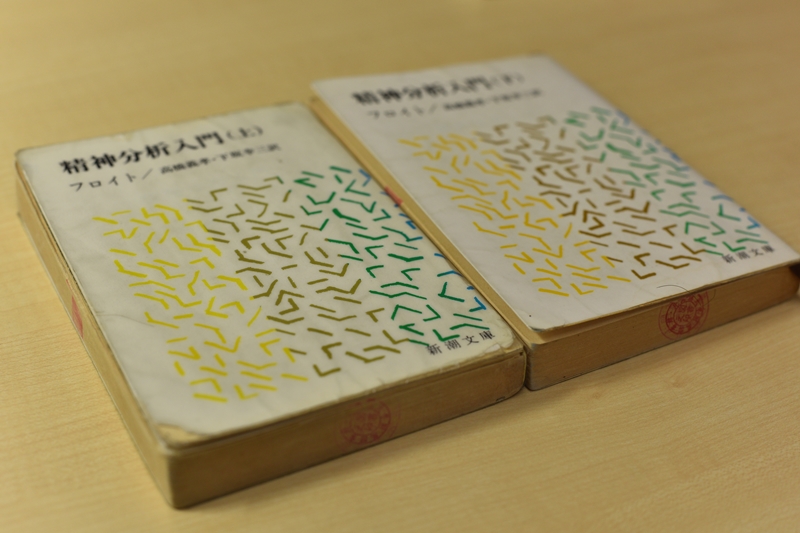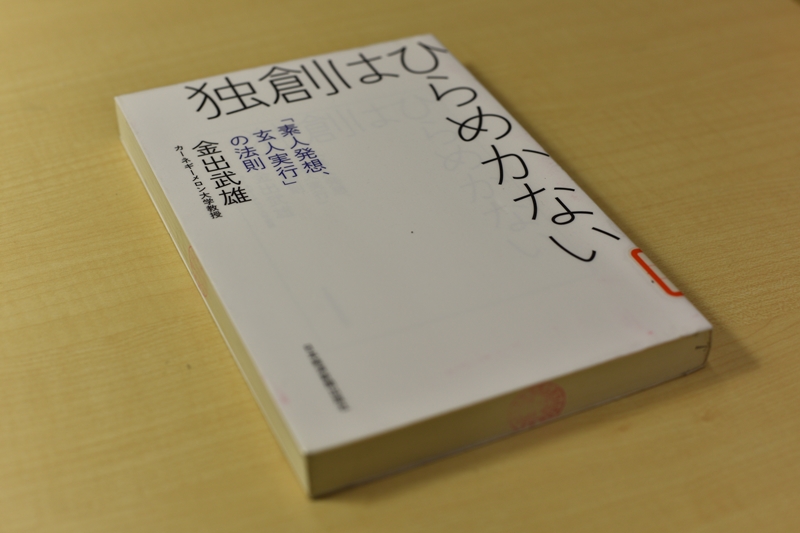前回の記事では、人とロボットのインタラクションの研究に取り組む小野哲雄さん(北海道大学工学部情報科学研究科教授)に、研究や小野さん自身のことについてお話を伺いました。この記事では引き続き小野さんに、推薦していただいた「精神分析入門」「独創はひらめかない」「人とロボットの<間>をデザインする」の三冊の本を基にインタビューを行いました。
【佐藤七海・総合理系1年/吉田のどか・総合文系1年/足達春樹・農学部1年】
『精神分析入門』(上下)ジークムント・フロイト著、高橋義孝、下坂幸三共訳(新潮文庫/1977)
19世紀後半~20世紀前半に活躍したオーストリアの精神科医、ジークムント・フロイトによる講義録をまとめた著作です。精神分析の創始者であるフロイトは神経症患者との対話を通して、人間の深層心理や無意識に焦点を当てる独自の手法を用いました。
この本をいつ頃お読みになりましたか?
中学生の頃です。こんな世界があるのか!と、衝撃を受けました。無意識に見る夢を分析するとその人が何を本当に望んでいるのかわかるとは驚きでした。しかし、フロイトの精神分析は他者による検証ができないという点で科学として成立しません。大勢の人を巻き込むフィクションを創り上げたけれど、科学たり得なかったといえます。
フロイトの精神療法は現在どのように用いられているのでしょうか?
今は精神分析家が患者の無意識の状態を発見するよりも、患者自身の気づきを優先するようになっています。精神療法の一つに患者の話を聞く来談者中心療法という分野がありますが、ロボットでも似た分野の研究者がいます。いわゆるELIZA(イライザ)、人工無能といわれるもので、「なんかつらいよ」と話しかけると、「そうですね、人生ってつらいものですからね」などと返事をします。簡単なパターンマッチで返答するだけですが、人間が何か意味や関係を見出したくなります。
精神療法でのフロイトの役割をロボットができるのですか?
人間を良い方向に導くことができればいいですが、トラウマに触れてしまった場合などに誰が責任をとるのかが問題です。ロボットによる精神療法はSF作家アシモフの提唱するロボット工学三原則(※)からはみ出してしまう気がします。ロボットの助けを借りることで人間が意味を見つけるというのが正しいあり方だと思います。
※アシモフのロボット工学三原則:
- ロボットは人間に危害を加えてはならない
- ロボットは人間に与えられた命令に服従しなくてはならない
- ロボットは前掲の第一法則、第二法則に反するおそれのない限り自己を守らなければならない
t
t
t
この本をどのような人に推薦しますか?
一見正しそうに思えますが、ほとんど彼の思い込みではないかと思います。なので、自分で価値判断ができる大学生以降に読むのをお薦めします。
『独創はひらめかない―「素人発想、玄人実行」の法則』金出武雄 著(日本経済新聞出版社/2012)
ロボット研究の世界的権威である著者が、発想と発明のエッセンスや問題解決法、説得のスキルにおける本質を語っています。
どうしてこの本を勧めようと思われたのですか?
この本の中には、研究のエッセンスが詰まっているだけではなくて、他の仕事にも役立つような若い人が知っておくべきノウハウがたくさん詰まっているからです。研究のエッセンスの観点からいえば、これは専門家があまり気づかないけれど、一般の人が困っている所に本当に解決すべき問題がある。そのために一般の人と問題を共有し、一般の人が望むものや解決して欲しいものの中からテーマをを見つけ出すことが重要で、問題を解決するにはプロの知識や技術が必要ということが述べられています。だから発想は素人の目線で実行は玄人の技術で行う、「素人発想玄人実行」ということが大事なことなのではと思います。それから若い人が知っておくべきノウハウの観点からこの本を読むと、研究をしていない方にもあらゆる場面で利用できる便利な知識を得られると思います。
「素人発想玄人実行」をご自身の研究でどのように用いていらっしゃいますか。
今までお話ししたことを僕なりに解釈して用いようとしているのですが、金出先生のようには上手にできないというのが実際のところです。「素人発想」にもかなりセンスが必要で、背景に技術力があるからこそ、「素人発想」から見て面白いものが見つけられるのではないかなと思います。
最後にどのような人にこの本を読んでほしいと思いますか?
30代、40代あたりの方達は自分のペースを定めてやってきている世代だと思うので、その前の皆さんのような大学生と、管理職になって、何て言ったらいいんですかね...様々な経験を積み、少し自分の考えに固執している人というか(笑)、そういう方にもう一度会社の仕事や、自分のプレゼンを振り返ってもらいたいので、読んでもらいたいですね。
『人とロボットの<間>をデザインする』山田誠二編 (東京電機大学出版局/2007)
この本は人間であるユーザとロボットや擬人化エージェントの“間”、つまり“インタラクション”をいかにデザインするかについて、その方法論と研究について書かれた本で、第3章では小野先生が執筆にかかわっていらっしゃいます。
この本を推薦した理由を教えてください。
この本は少し前のものなのですが易しく書かれていて、最新の論文よりも僕が研究してきたヒューマンエージェントインタラクションという分野をよくわかってもらえると思って推薦させていただきました。
どういう経緯で3章の執筆に至ったのですか。
京都の研究所にいた時に始めた「ITACOシステム」をはこだて未来大学にいた時にも続けていたら、面白いと言ってくれる人が結構いたので紹介しておこうと思って執筆しました。
「ITACOシステム」とはどのようなものですか。
わかりやすく言うとたまごっちや初音ミクのようなキャラクターが自分と仲良くなっていろいろなメディアやデバイスに乗り移ってユーザをサポートしてくれるというシステムです。例えばたまごっちに「暑いな」と言ったら「エアコンつけるね」と言ってエアコンに乗り移ってエアコンを調整して戻ってくるというようなものです。プログラムのコアな部分(キャラクターの心)は同じでメディアだけ変わってしまうような感じですね。
この本をどういう人に読んでほしいですか。
卒業論文に取り組み始めようと思っている人や大学院に進学して修士課程でどのような研究テーマを選択しようかと考えている学生などに読んでもらいたいです。結構技術的な部分もちょっと入っているので全く一般の人に読んでもらうよりも、研究してみたいけど何をしようかなという人に読んでもらったほうがいいですね。
この本を通してどのようなことを伝えたいですか。
読んで面白いというよりも「あ!こういう分野もあるんだ」と気づくきっかけになってほしいと思います。すでに研究をやりたいというモチベーションを持っている人に読んでもらってこういう選択肢もあるんだということを伝えたいですね。
これらの3冊の本を通じて様々な観点からロボットや私たち人間についてより深く知ることができます。インタビュー記事を読んで小野さん自身や小野さんの研究分野に興味を持った方は読んでみてはいかがでしょうか。
※ ※ ※ ※ ※
この記事は、佐藤七海さん(総合理系1年)、吉田のどかさん(総合文系1年)、足達春樹さん(農学部1年)が、全学教育科目「北海道大学の”今”を知る」の履修を通して制作した成果物です。