人文・社会科学総合教育研究棟W103共同講義室にて、北大教員による無料の公開講義(https://hokudaisai.com/event/event-itr/p-class.php) が開催されました。
そのうち、獣医学研究院 の坪田 敏夫教授が開講する「世界のクマの調査研究と現状〜ホッキョクグマとヒグマを例にして」を受講しました。
坪田先生はこれまで40年以上、クマの生態や生理に関する研究を行っています。講義では、ヒグマの生態やこれまでに坪田先生が行ったヒグマやホッキョクグマの生態調査、人とクマの軋轢とその解決に向けた取り組みについてお話ししていただきました。この記事では、その中でもヒグマとホッキョクグマの調査について、相違点などをまとめました。

講義ではヒグマに関する様々な調査が紹介されましたが、今回の記事では特に、2009年から2014年に行われた、ヒグマの現在地追跡調査(GPSリアルタイムテレメトリー)について取りあげます。追跡調査とは、GPS機能付き電波発信機をヒグマに取り付け、長期間ヒグマの位置を追い続ける調査方法です。具体的には、生け捕りして麻酔をかけたヒグマの首に発信機を取り付けたのち、放獣(捕獲した動物を野生にかえすこと)します。発信機はNTTドコモが開発したもので、携帯電話のアンテナ網圏内であればヒグマを追跡できます。また、バッテリーを搭載可能なので、4か月ほどはヒグマを追跡できるそうです。
坪田先生によると、GPS機能付きの電波発信機をヒグマに取り付ける調査は、たとえるなら「ヒグマに携帯電話をもたせ、定期的に今どこにいるかおしえてもらう」調査とのことです。この調査により、ヒグマがどのくらいの距離を移動するのか、どのような環境を利用しているのか、などを把握することができます。
ヒグマに関する話題の次は、研究クラウドファンディングによって行われた、カナダのチャーチルでのホッキョクグマ生態調査について紹介されました。
この調査では、ヘリコプターで上空から海氷上の足跡を探し、それをたどってホッキョクグマを見つけるそうです。ホッキョクグマを発見したら麻酔で眠らせ、体重以外のデータを計測したり、GPSのイヤータグを装着したりします。
ヒグマの場合、GPS装置は首に取り付けるタイプを使用していました。しかしホッキョクグマの場合は、水中を泳ぐために体が流線型になっているため、首輪タイプだと外れてしまうことがあるそうです。そのためホッキョクグマの調査では、ピアスのように耳に取り付けるタイプのGPS装置を使用します。ただしバッテリーをつけることができないため、追跡できるのは1か月間ほどだそう。
調査では、ホッキョクグマがかまくら状の巣にいるアザラシを襲って食べた食痕(食べ残した骨など)を見ることができたそうです。またGPS追跡によって、ホッキョクグマが海氷上から陸に生活圏を移す時期の特定ができました。ホッキョクグマは、海氷がある時期は氷の上でアザラシなどを狩って生活し、氷が解ける時期になると陸に移動します。通常ホッキョクグマは、7月までは海氷上で生活をするとされていますが、先生が参加した調査で、GPSを装着したホッキョクグマは6月に陸に移動した、というデータがとれました。この理由として、地球温暖化により氷の解ける時期が早まっていることがあげられています。
ホッキョクグマは、ヒグマと異なり完全に肉食に進化した動物です。ホッキョクグマはアザラシを主食とし、海氷のある期間はアザラシを狩ることができますが、氷が解けて陸上で生活する期間はほぼ食料がない状態で過ごします。つまり、地球温暖化により海氷がある期間が短くなると、ホッキョクグマはより長い期間絶食して過ごすことになります。地球温暖化による影響によって、ホッキョクグマは今後45年の間に個体数が半減、もしくは60%以上減少する可能性が示唆されています。
ホッキョクグマのように絶滅の危険性が示されているクマがいる一方で、ヒグマのように個体数が増加し、人間との軋轢が大きくなっているクマもいます。
最近は、ヒグマの市街地出没や、人身事故に関するニュースを耳にする機会が多くなってきています。この理由として、ヒグマの個体数が増えて分布域が拡大していることや、猟師の減少によって人間を恐ろしいものと認識しないヒグマ、いわゆる「新世代クマ」の増加があげられました。
坪田先生はヒグマの管理に関して、加害個体の排除や、大都会周辺のヒグマ密度のみ減少させるなど、シカやイノシシの管理より細かい対策が必要であるとお話しされていました。また、個人ができる一番のヒグマ対策は「出会わないようにすること」であり、そのために必要な知識を身に着けることが重要であると最後にまとめられていました。
ヒグマに出会わないために、そして万が一ヒグマに出会ってしまった時のために必要な知識は、市民団体の「ヒグマの会」(https://www.higumanokai.org/)が発行する「ヒグマノート~ヒグマを知ろう」(https://www.higumanokai.org/brown-bear-note/)に詳細がまとめられています。
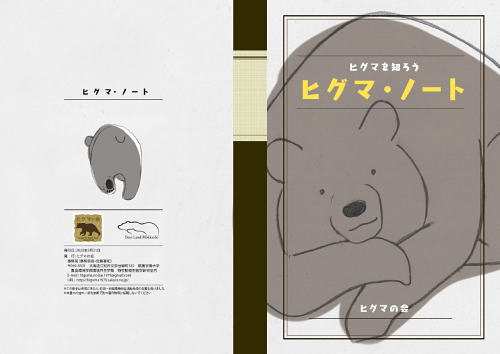
いいね北大で過去に坪田教授にインタビューした記事はこちらからご覧いただけます。
#78 自らの「生き様」を確立せよ(1)~野生動物研究を通じて
https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/like_hokudai/article/6531
#79 自らの「生き様」を確立せよ(2)~いのちに触れる研究人生を創り上げた3冊(書籍紹介)
https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/like_hokudai/article/6540
#197 愛して、恐れて~クマを保護しながら、管理する~
https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/like_hokudai/article/29469
