執筆者:佐藤このみ(2022年度SD実習/学生)
アーティストとして作品づくりから書籍の執筆まで、幅広く活躍される中で社会に問いを投げかけている彫刻家・小田原のどか先生にご講演いただきました。
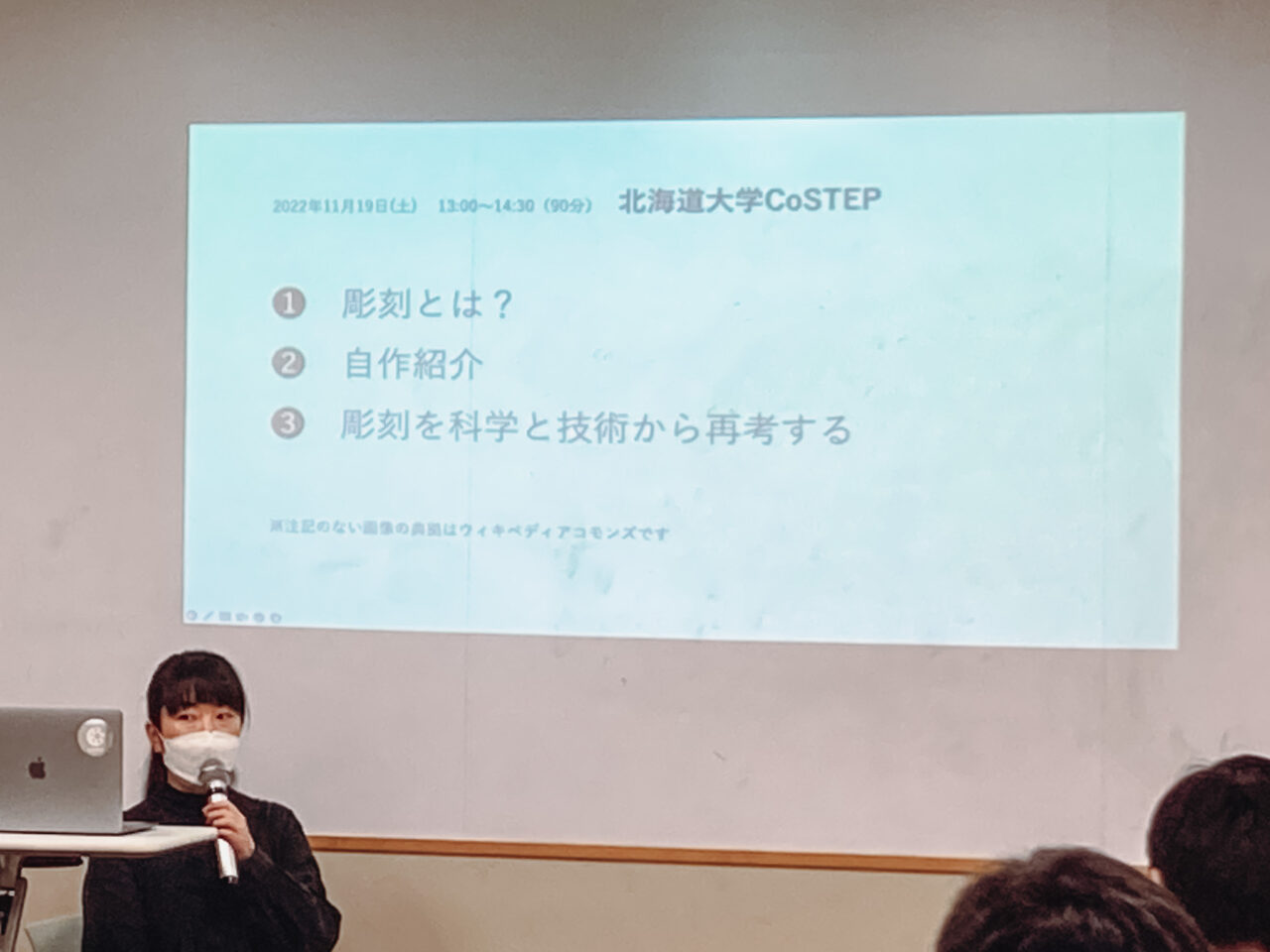
絶え間なく存在が問われ続ける彫刻
「彫刻って、発見され、何度も何度も破壊され、想像されるものなんです」。小田原先生の問いかけに「どういうこと?」と思ったあなたはラッキー。彫刻の見方、変わります。
小田原先生は、いくつかの事例を紹介しながら絶え間なく存在が問われ続けるものとしての彫刻を解説します。例えば、絶え間なく存在が問われ続ける彫刻の事例としてロダンの「考える人」や「地獄の門」など、言わずと知れた作品は、実は元のオリジナルをコピー&ペーストで作られていたり、「サダム・フセイン像」や「レーニン像」、南部戦争の「英雄」をたたえた「コロンブス像」は何度も破壊される対象になってきたのだといいます。
これらの事例が指し示すものは、彫刻は永遠不滅なものでも、ただそこにあるものでもないということです。コピー&ペーストしたり、破壊したり、何度も作られたりする彫刻は、彫刻は普遍的なものでないばかりか、時代の要請に応じて形として変化してきたもの、と考えられます。
彫刻そのものが変わったのではなく、彫刻をまなざす私たちが変わったのならば、彫刻とはその時代を示すまさに「象徴」ではないか。「彫刻は私たちが思っていることを如実に表す鏡のような存在である」。小田原先生の関心はまさに、ここにあります。
彫刻はどこからきたのか
さて、街を歩いているとあちらこちらにみられる彫刻。これらはいつ、日本にやってきたのでしょうか。
実は彫刻が日本に導入されたのは大正時代。富国強兵の過程で彫刻家たちを養成し、「公共の場」をつくるために数々のモニュメントが彫刻家たちによって手がけられました。その一例が、北村西望によって作られた「寺内正毅像」です。
第二次対戦中、彫刻は空白期として歴史に刻まれることはありませんでした。戦争を想起させる彫刻は戦後、撤去されることとなります。
「平和」を象徴するものは

戦後、軍国主義のシンボルだった彫刻は、平和を象徴するものへ姿を変えます。「寺内正毅像」の代わりに台座に置かれたのは、菊池一雄によって手がけられた三体の「裸婦像」でした。
電通が「広告平和消費」という名で宣伝広告とタイアップしていたこともあり、『毎日新聞』は「軍国日本から文化日本への脱皮を象徴する」(毎日新聞)と報じています。この像は、日本という国のあり方が大きく変わったことを象徴するものとして伝えられました。
これを受けて小田原先生は、「なぜ女性なのか、なぜ裸体なのか」同じ女性として、思いを馳せないわけにはいきませんでした。今、公共空間にはたくさんの裸婦像があります。軍国の象徴を埋めるために作られた裸婦像をみて、「果たしてこれは新しい日本のシンボルなのか?」「なんの新しさがあるのか?」を問うことになります。これらの考察を踏まえて小田原先生は、2019年に開催されたあいちトリエンナーレで同じ大きさの台座を、方角を皇居に向けた方角に設置しました。それが以下の作品です。

長崎にて
小田原先生が平和を考えるきっかけになったもう一つの作品があります。爆心地に建てられ、2年で撤去された標柱です。
小田原先生は、「どうして慰霊や追悼の意味ではなく、記号的な意味を指す山根の標柱が2年間だけあったのか」を問い、この標柱をモチーフに作品を作りました。それが以下の作品です。

この作品を作るにあたって、自ら発光し、顧みられなくなったために今はもう失われつつある技術を使うことが大事だったという小田原先生。
この作品をつくると同時に小田原先生の頭に引っかかったのは、北村西望によって戦後作られた「平和祈念像」です。
「長崎の平和祈念像は長崎で生きてきた人たちの苦しみをある種隠してしまうのではないか」という問い。また、 もともと国の偉大な象徴を作っていた西望が平和祈念像を作成することは、連続性しかないのではないか、といった問いが浮かび上がります。しかし、このことへの反省はなされていないのだと小田原先生はいいます。
作品を鑑賞してもらうにあたって望むもの
ご自身のリサーチと考察から作品を通じて社会に深い問いを投げかけている小田原先生。
作品を鑑賞してもらうにあたって、どんな鑑賞の仕方でも構わないから、なんで台座がここにあるの?ネオンの展示があったの?と思った人がネット上にアクセスできるようにすることを意識しているといいます。
鑑賞した人のコンディションは色々であるため、いつかその人が知りたいと思った時にアクセスできる道筋を作っていくことが大事だと考える小田原先生。その背景を知るということをしなければ、作品を経験したことにならないといいます。
終わりに
「彫刻」と聞くと「どこか不変なもの」とイメージされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私は、彫刻がこんなにも動的で劇的な変容を遂げてきたのだと驚きが隠せませんでした。彫刻がいかなる形を遂げていったのか。その時々の時代から彫刻を捉え直そうとする小田原先生の取り組みは、普段何気なく目にしていたアートと社会の関係を考えるきっかけになりました。社会と彫刻がいかにして相互に影響しあい、摩擦しているのか。社会と科学技術の間に立つ科学技術コミュニケーターにとって、重要な視座を提供いただいたといえます。小田原先生、ありがとうございました。


