高橋聖樹(2025年度選科A/予備校講師)
科学哲学を専門とする松王政浩先生(北海道大学OECセンター長/理学研究院 教授)による講義が行われました。

1. 科学技術コミュニケーターの踏み込むべき領域
科学技術コミュニケーターは科学の専門家と非専門家の間をつなぐことで、科学的知識を非専門家にわかりやすく伝えたり、非専門家の意見形成を補助したりする役割を果たしているイメージをお持ちの方が多いかと思います。
そのようなコミュニケーションにおいて、専門家以外にも「見える部分」(仮説、数理モデル、実験、実験方法、データ、結論)だけに基づくのは不十分であると考えられます。なぜなら、科学技術に関連する知識はそれだけで成り立っていないからです。
例えば、モデルやデータの解釈、背景となる理論・知識、専門家間の暗黙知などは「専門家以外には見えづらい部分」です。なかには因果判断の基本的条件など「専門家でも見えづらい部分」もあります。さらに、科学技術に関する意見形成において、科学的知識以外にも規範的知識も大切になってきますが、その意見の是非をどのような価値基準で評価すべきか(すなわち価値判断)については「専門家・非専門家双方にとって見えづらい」です。
このような「見えづらい部分」がミスコミュニケーションを引き起こす原因ともなり得るため、科学コミュニケーターはこの領域に踏み込む必要性がありますが、今回の講義で扱う科学哲学はこのような「見えづらい部分」を探る学問です。
2. 科学者の価値判断をめぐる四つの立場
講義の中心は、科学哲学の中でも「科学者の価値判断」に関する議論です。以下の四つの立場が紹介されました。
- ラドナー的立場:科学者は積極的に価値判断をすべきである。
- ジェフリー的立場:科学者は価値判断をすべきでなく、それは社会が担うべきである。
- スティール(1)的立場:科学者は確率的判断にとどまりつつも、政策利用を考慮し、情報を加工すべきである。
- スティール(2)的立場:情報が政策にどのように使われるかを考慮し、誤った利用がなされていないかチェックしつつ、情報を加工すべきである。
3. 三つの事例から学ぶ
講義では、実際の社会における三つの事例を通じて、科学と価値判断の関係がどれか一つの関係に絞られるのか、あるいは科学の種類によるのか、科学の種類によるとすれば何が基準なのかが検討されました。
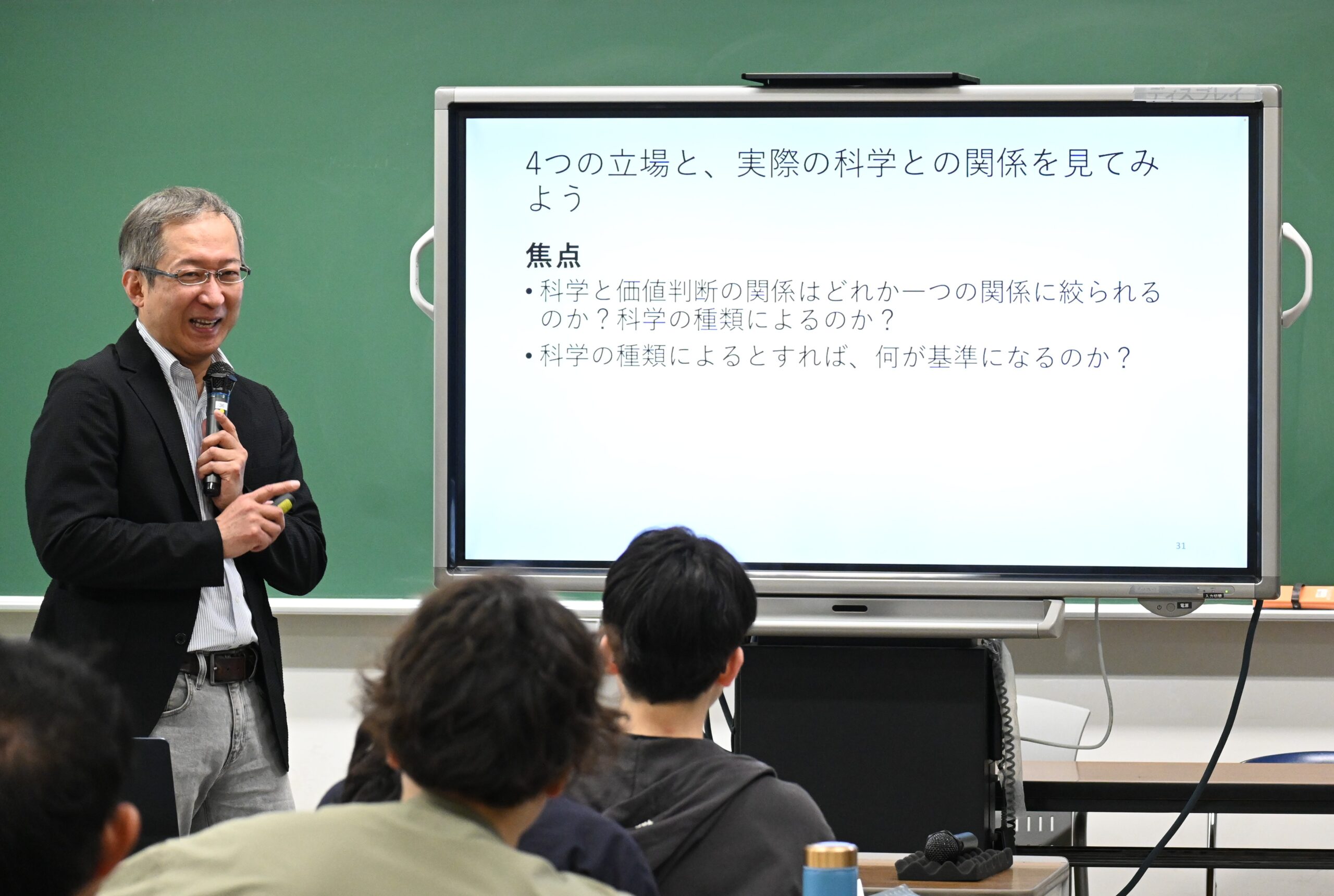
(1) IPCCの事例
気候変動をめぐるIPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change:気候変動に関する政府間パネル)の役割は、基本的にはスティール(1)的立場に近いです。すなわち、政策を直接的に決定するわけではなく、不確実性を含めた科学的情報を加工して提供する役割です。ところが、2007年にIPCCが緊急メッセージとして気候変動に対しての行動変容を呼びかける声明を発した際には、ラドナー的な積極的な価値判断の側面も見られました。
このように、同じ組織であっても立場が変わることがありますが、気候変動の科学は、科学側が提示する情報に対して社会的な選択の幅の広さを持つ分野であるからであると考えられます。つまり科学の種類によって社会的選択の幅が異なり、当てはめるべき価値判断の類型が異なることが示唆されています。

(2) 新型コロナウイルス感染症対策の事例
コロナ禍においては、科学者が果たすべき役割が常に問われてきました。未曾有の事態を目前にして、専門家会議においてSIRモデルをもとに市民行動を誘導するラドナー的立場へと発展しましたが、専門家会議の解散後に科学者の役割が再考察され、科学者はその立場を変化させていきました。
この立場の変化の理由も社会的な選択の幅の広さがあったからだと考えられます。また、科学者の一方的な判断ではなく、広範な市民の声を反映させることの重要性も浮かび上がりました。
(3) 地震学の事例
最後に地震学の事例が取り上げられました。地震の評価においては「地震が起こる確率評価に対する不確実性」(二階の不確実性)が焦点になります。具体的には、例えば福島県沖のプレート境界地震の発⽣確率は「30年以内に7%以下」と予測されていましたが、ここで予測されている確率については、同様な過去の地震データがほとんど無かったため、確率の信頼性は低いと評価されていました(発生確率評価の信頼度はD)。このような二階の不確実性評価についても様々な立場が存在します。
- 「発生確率(⼀階の情報)だけでは政策⽴案が難しいので、政策を⽴てやすくする補助として信頼度(二階の不確実性評価)が役に立つ」というスティール(1)的立場
- 「確率(⼀階の情報)に基づいて安易に政策に適⽤した場合の影響を考慮するために二階の不確実性評価はあるべき」というスティール(2)的立場
- 「信頼度(二階の不確実性評価)がかえって政策に恣意的に使用されるので信頼度を付与すべきではない」というスティール(2)的立場
今回講義では扱いませんでしたが、ラクイラ地震裁判のように、二階の不確実性をめぐってどの立場を取るべきかに関しては論争になることがあります。

4. おわりに
私はCoSTEPに参加する前に、「科学とは何か」をもっと深く知りたいと思い、科学哲学を学んでいた時期があります。その学びの中で、松王先生のご著書『科学哲学からのメッセージ──因果・実在・価値をめぐる科学との接点』も拝読したことがあり、今回の講義も非常に楽しみにしておりました。
講義を通して、科学技術コミュニケーションにおいて「見えづらい部分」に注目することの重要性をあらためて理解することができました。私は職業柄、科学的知識を人に伝える機会が多いのですが、今回の講義を通じて、自分自身や一般的な実践における科学技術コミュニケーションの不足点を認識することができ、大変有意義でした。
また、現代社会のさまざまな問題が複雑に感じられ、科学者を取り巻く議論をうまく整理できないことも多々ありましたが、科学哲学における価値判断論を通じて四つの立場の違いという視点から考えることで、問題を整理する手がかりが得られ、参考になりました。
科学技術コミュニケーションにおいて上記の「どの立場であるべきか」という問いなどはまだ十分に結論が出ているわけではありませんので、今後の科学哲学や科学技術コミュニケーションの発展が求められると思います。私自身も、引き続き学びを深めつつ、より実践的なかたちで関わっていけるよう努めてまいりたいと思います。

