作成者:松永博充(選科A)
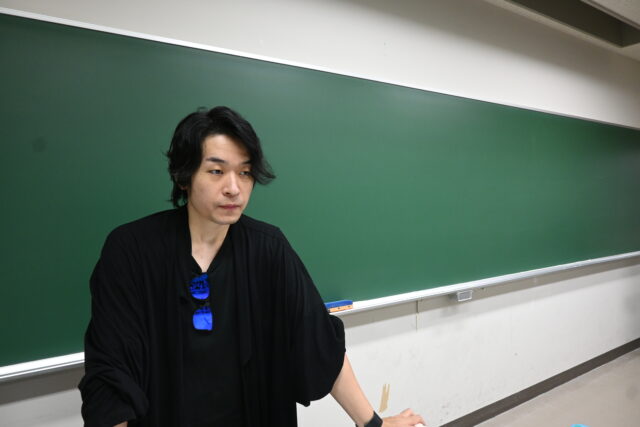 (講師を務めていただいた阿部幸大先生/筑波大学人文社会系助教)
(講師を務めていただいた阿部幸大先生/筑波大学人文社会系助教)
今回の講義は、阿部先生の著書『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』(2024年、光文社)の「原理編(アーギュメント・アカデミックな価値・パワグラフが論文の三本柱である)」を中心に、アーギュメントの本質とその重要性について体系的に解説されたものでした。
論文とアーギュメントの関係について、阿部先生は「論文とは、ある主張を提示し、その主張が正しいことを論証する文書である。この主張を、英語ではアーギュメント(argument)と呼ぶ」と説明されました。講義を通じて、アーギュメントとは決して一部の分野に限られた技法ではなく、すべての学問や実践に通底する構造であるというメッセージが強調されていました。
私自身、これまで自然科学系の研究においてIMRAD形式(後述)で論文を執筆してきました。背景や方法、結果に重点を置き、読み手にとっての再現性を担保することを最優先としていましたが、「自分はその研究対象について何を主張したいのか」「なぜその主張が成り立つのか」を深く考える機会が少なかったように思います。たとえば、ある調査結果をまとめた際にも、「データがこう示している」という記述にとどまり、そこから何を論証したいのかという視点が弱かったと感じています。
今回の講義を通して、「自分自身の問いと主張を明確にし、それを根拠とともに読み手に伝えること」が論文であると再認識しました。今後の実践では、自らの主張とそれを支える論拠を構造的に構成する、つまり「アーギュメントをつくる」という視点を重視していきたいと考えます。
なお、本レポートの作成にあたっては、講義内容に加えて、阿部先生の著書『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』も参考にしています。論文執筆に関心のある方には、分野を問わず一読をおすすめしたい一冊です。

1.講義内容のポイント
(1)論文とアーギュメント
論文とは「ある主張を提示し、その主張が正しいことを論証する文章である」と定義され、その中心にあるのが「アーギュメント」であると説明されました。アーギュメントとは、単なる主張ではなく、「論証を要する主張(テーゼ)」であり、論文の核となる構成要素です。自身が提示するアーギュメントを明確に意識し、それを自力で論証できるかどうかを見極めることが、論文作成の出発点であると強調されました。
(2)アカデミックな価値をつくる
研究対象の名称そのものを「自分の専門」だけで捉えるのではなく、「その対象についてどのようなアーギュメントを展開するか」によって、研究の価値が決まると述べられました。研究の意義や独自性は、対象の選定そのものではなく、どのように問いを立て、論証するかにかかっています。論文とは、単なる情報の整理ではなく、自らの問いに答えを与えるプロセスであり、学術的価値の創出するそのものであるという姿勢が示されました。

(3)パラグラフ・ライティング
論文は複数のパラグラフ(段落)で構成され、それぞれのパラグラフが明確な主張(ミニ・アーギュメント)をもち、全体のアーギュメントを支える構造を持つべきであると説明されました。読み手にとって論理的に読み進められるよう、各段落の論理構成に注意を払う必要があります。
特に、論文の冒頭で提示されるアーギュメントは、しばしば飛躍しているように見えるため、各パラグラフを用いてその飛躍を論理的に補強・展開していく必要があります。
(4)IMRADとは
自然科学系論文で広く採用されているIMRAD形式(Introduction, Methods, Results, And Discussion)についても触れられました。IMRAD形式は、再現性と客観性を重視する科学的な論述に適しており、研究の背景・方法・結果・考察を明確に分けることで、論理構造が明確になります。一方で、人文系の論文はこのような明確なフォーマットが存在しないため、アーギュメントの構築が一層重要であり、Introductionで提示することが必要であると述べられました。

2.おわりに
本講義を通じて、論文におけるアーギュメントの重要性を体系的に学ぶことができました。自然科学系の論文では、IMRAD形式に代表されるような明確な構成が一般的ですが、人文社会系の論文では必ずしも形式が統一されておらず、構成や論理展開が自由である分、アーギュメントの重要性が一層問われます。その点で今回の講義は、論文作成における論理構成の基礎を学ぶうえで有意義な機会となりました。
論文執筆においては、論文の書き方に関する書籍は多く存在し、学生であれば指導教官によって異なる論文スタイルを求められることも少なくありません。しかし、本講義はそれらの個別スタイルを超えて、アカデミック・ライティングの根本的な原則を示してくれるものであり、今後の研究・執筆活動に大きな示唆を与える内容でした。
阿部先生は、論文とは「アカデミックな価値を持つアーギュメントを提示し、それを論証する文書である」と定義し、それを支える要素として「アーギュメント」「アカデミックな価値」「パラグラフ」を三本柱として挙げました。
アーギュメントは決して堅苦しいものではなく、むしろ「自分がなぜそう考えるのか」を明確にし、他者とつながるための基本的な道具です。今回の講義を通して、それは論文執筆のためだけでなく、研究の価値を社会に伝え、自らの思考を深めるためにも、欠かせないものだと学びました。
今後、科学技術コミュニケーターとして研究と社会をつなぐ実践を重ねる中で、アーギュメントの技法と姿勢を意識的に取り入れていきたいと考えています。
最後に、本レポートはアーギュメントを意識して作成してみましたが、いかがでしょうか。
皆様からのご意見をお待ちしております。

(阿部先生、ありがとうございました)
注・参考文献
阿部幸大,2024,『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』光文社

