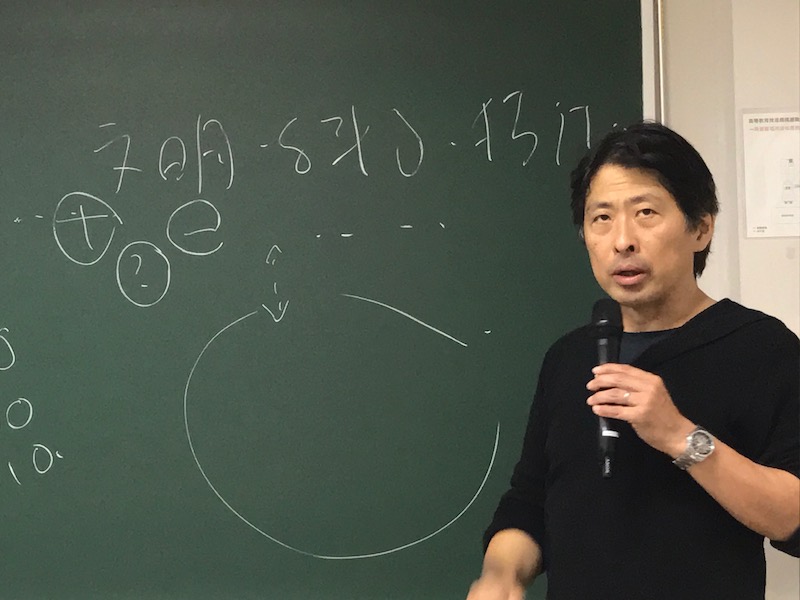上林菜月(2016年度本科/学生)
「身体に関わる技術 どんな理由でどれほど肯定されるか」と題し、立命館大学の立岩真也教授から、障害者と障害者を取り巻く科学技術との間に生じている問題について、お話ししていただきました。
社会に対して懐疑的に向き合う時代
人々が社会に懐疑的に向き合い始めたのは1970年ごろです。1960年代の「科学はすごい、未来は明るい」と言われていた高度成長の時代から一転し、学園紛争や公害問題などをきっかけに、本当にそうなんだろうか、と社会に疑問が生じ始めました。
文明や科学・技術について人々が疑問や不安を持ち始めると、だんだんと世間の考えは「自然なものがいい、エコなものがいい」という考えに変化していきました。しかし、文明や科学・技術がもたらしたのは悪いことだけではありません。人工のものと自然のものとを対峙させて考えるだけでは、どうも上手くいかないこともあるようです。
複雑化する問題
1970年を象徴する出来事の一つに、水俣病に関わる社会運動が挙げられます。四大公害裁判が始まり、ちょうどこの頃から、水俣病は社会的に注目を浴び始めたのです。当時、水俣病のように公害によって傷つけられた身体は誰のせいなのか、責任の追及や救済を求める声が上がりました。その一方で、そういった活動に対して「障害のある身体を否定しているのではないのか」という批判も存在しました。
「障害は治るべきもの、ない方がいいものであり、治すための技術は当然に肯定される」と考えられていますが、必ずしもそうではありません。障害がある身体は「自然」であり、人の手が加えられるべきでは無い、という考えもあるのです。
しかしその批判も、簡単に受け入れられるものではありません。
例えば、人工呼吸器が無いと生きられない難病を患って生きている人に対して、呼吸器をつけずに「自然に」死ぬほうがいいと考えるのか、「人工呼吸器」で延命するほうがいいと考えるのか。「自然がいい」という考えであればそれは、この患者に対して「死ぬほうがいい」という考えを持っているということなのでしょうか。
(立岩先生の著書も絡めながら講義が進んでいきます)
複雑化した問題をどう解すのか
「身体に関わる技術について、自然に対して技術が否定的に語られるようになってきて、問題が複雑化したのではないか。」
と立岩先生はおっしゃいます。そこで、立岩先生は「技術」に対して「自然」を対峙させるのではなく、自分が何が「良い」ことで何が「嫌」なことなのかで分けて考えることを私たちに提案します。
例えば、病は「死ぬかもしれない」「苦しい」ものだと定義すると、病気になるのは「嫌」なことで、これを回避したいと考えます。つまり、病気を治療する技術は肯定されます。一方で、障害は「できない」「人と違う」ことと定義すると、これらは必ずしも「嫌」なものではありません。つまり障害に関する技術が、いつも肯定されるわけでは無いことが見えてきます。
できないことは悪いことか
障害を持つということを仮に一言で定義すると「できない」ことです。一般の人が生きるためにやっていることを、障害者の人はうまくできません。できることはいいことです。しかし、できないことは本当に悪いことなのでしょうか。
「できない」ことを「できる」ようにするためには、3つの手段があります。一つは障害などを治してしまうこと。次に道具などを使うこと。そして三つめは、できる人から必要なものを譲ってもらうことです。
生産者・消費者の関係のように、すべての人間がすべてのことをできる必要はありません。病気と違って、障害者の人が「できない」ことは、誰かがかわってあげることができるのです。
現在は、科学や技術により障害を治したり道具を開発したりすることで、「障害者が何かをできるようにする」ことに重点が置かれています。障害者ができることが増えると、周囲の人が楽をできるかもしれません。しかし、難病や障害によっては、今までに成功した技術がないものも存在します。できるようになる見込みがない難病や障害について、どれだけ技術を開発し続けても、その技術を実践する障害者さんにとって苦痛でしかないかもしれないのです。